カメキチの目

歳をかさね、昔を思いだし、過去をなつかしむのは、「年より」とよばれるまで生きてきたからこそできる。
そのこと自体を天に感謝せねばならない。思うたび、自分より若くして逝った人たちを想わないではおられない。
中学卒業まで、すぐそこまで迫った山やまに四方をかこまれ、「辺鄙」という言葉がピッタリの故郷ですごした。
正確には、実家は抵当物件にはいっていたので、一時期は母の里で暮らしましたが、そこも似たりよったりのところでした。
ひとくちに「故郷」といっても、その地形的範囲は広い。
そのなかで、私の家は山のふもとにはりついたような十数軒(集落)のなかの一つ。
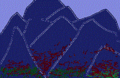
山間のそこは太陽が半日しか射さない、「半日村」。
のちに、裏山の崖からは離れたがこんどは川のそば。どちらにしても、先日の九州北部豪雨のような大雨におそわれたら…。いままでのところ無事に過ごせているのは、運が良いとしかいえない。
集落は多くがよく似た姓を名のっており、遠い近いの差はあっても、同族の血縁にあったようだ。
ちなみに私の両親も、母の里はふた山こえたくらいの同じく辺鄙なところで、ふたりは「いっしょにさせられた」。
むかし庄屋であったとか、伝統、名のある家の維持、継続のためにというよくあるテレビドラマとはまったく違います。
年ごろを迎えた母と、戦争から還った父が、適当に(言葉が悪い…か。でも「適当」というのは「仕方なく」も「いい加減」というニュアンスもありますが、それを含めて、いまの私は自分にとっては「いい《good》」ふうにとらえています)結婚した。
その時代は、縁があれば(というか「縁をつくる」「縁を引きよせる」。よほどの理由があるとか、本人の「結婚はイヤだ」という意志が強ければ別だったのでしょうが)結婚し、子どもを生み、育てるという生き方が一般的だったのだろう。
近所の十数軒の内には、近親結婚に近かったからか、今でいう知的障害の兄妹(私には「又いとこ」)がいた。
当時は古くからの因習が支配的で、又従兄の方はおだやかな性格だったのでよく見かけたが、又従姉はときどきわけのわからないことを大声で叫ぶので、(そういう言葉があることは後に知ったが)「座敷牢」(じったいは暗くてジメジメしていたであろう「納戸」)に閉じこめられていた。
ちょっと横溝正史の金田一世界みたいで、おどろおどろしいけれど、父方の一族には自殺者もいた。しかも複数。
こう書くと、「特殊」な世界のようだけど、当時の日本のいなか、村々であまり珍しいことではなさそうです。
そのときから半世紀もたったというのに、故郷の風景はほとんど変わっていない。
つまり、東京をはじめ都会はひと昔さえわからないほど街なみ、景観が変化しても、みごとなほどに辺鄙な田舎は変わっていない。
要は、もうけ・利益いちばんの資本主義の社会にあっては経済的な利用価値がないわけだ。
土地や景観の利用についてはなにも有効な手だてがはかられなかったということ。
経済・政治からは取りのこされたわけだ。
しかし変化がないということは、(「いまになって見れば」ですが)見方によっては「維持」につながるわけで、よくないこととはいえない。つまり「定常」。
が、しかし明らかに廃屋が目だち、もともとが猫の額ほどの田畑は荒れほうだい。そこがかつては耕作地だったとは思えない。
初めに十数軒と書いた集落に、いま人が住んでいるのは数軒くらいしかない。
この中に、私の弟がいます。たったの数軒でも共同作業、昔からの地域行事、回覧板まわし、行政の下請け業務(たとえば納税)などがあり、組長の当番が早く回ってくるとブーブー言っています。
また、一族の墓所が急峻な山肌にあり(障害者の私がそこまで自力で登るのはムリ。弟に背負われ恥ずかしかった)、自分が元気なうちは「墓守り」もせねばと言っているのですが、彼ができなくなれば(独身なので子どもはいない)、先祖代々の墓も荒れはて、消滅の運命か…
まあ、それもヨシとしなければならないだろう(「ヨシ」ではなく「しかたない」が本音)。
「墓」は自分たちの問題としてもさしせまっています。私たちが死んで、子どもに「墓」という象徴、記念、祈り《合掌》の対象物を作り、そこに骨を納めてほしい、あるいはどこかの寺院に納骨してくれとはまったく願っていません。
もちろん死ねば何もできないので、実際は子どもたちの好きにまかせるほかありません(自分が子どもの立場では、父や母の望むとおりにはしましたが)。
自分の来し方を思うと、つくづく私は身勝手な人間だと思う。自分で思わなくても他の人から「勝手な人だなあ」と言われるだろうけれど、しかたない。
人生は、自分の力ではどうにもならないものがあるのである。
ところで、「ひと口に『故郷』といっても、その地形的範囲は広い」と初めに書いた。
私の集落は「辺鄙くらべ(秘境とまではいかない。そのへんが中途半端なので秘境を宣伝した「観光地」にもならない)したら、よそには負けない」ほどだが7㎞も進めば、地域の中心地、公共施設もあり商店がいくらか集まる「小さな小さな繁華街」に出る。
「小さな小さな繁華街」は、日本全国どこでもあるように「なんとか銀座」と呼ばれていた。
〈続く〉